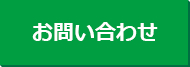トップメッセージ
化学の力で人と社会をつなぎ、
持続可能な未来に向けて新たな価値を創出し、
社会に必要とされる企業であり続けます。
代表取締役 社長 棚橋 洋太
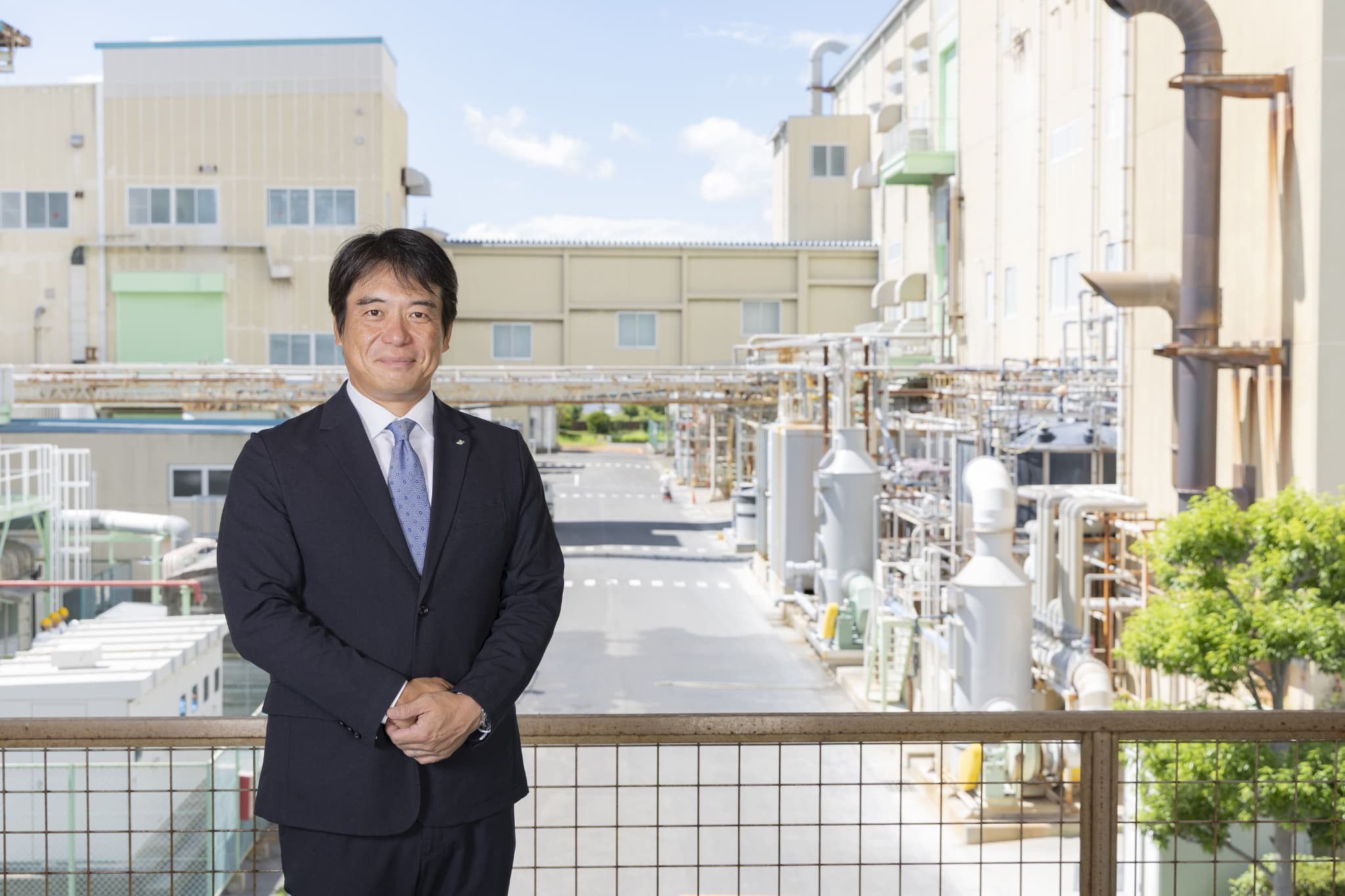
統合報告書発行により、目指す方向性が広く共有された
当社は昨年、初めて統合報告書を発行しました。財務情報とESG情報を一体的に開示したことで、株主の皆さまから「会社の方針や考え方が総合的に把握できた」というポジティブな反応をいただいたほか、従業員からも「会社全体として目指す方向性が理解できた」という意見が出るなど、目の前の仕事に忙殺される中で、部署や拠点を超えて想いを共有できたことが評価されています。私自身、これまでは「成果が認められた」ことと「成果は出ているのに情報発信がうまくできなかった」ことへのもどかしさに悩んでいましたが、統合報告書の発行により、そこが目に見えるようになったと感じています。MVVとして再整理した企業理念や方針をはじめ、長期戦略や中期経営計画(中計)など、統合報告書に掲載する前提で、社外の方にも分かりやすくまとめようとする意識が進んだように思います。
お取引先との信頼関係で形作られた当社のビジネスモデル
当社は、創業130年を超える歴史を持つ化学品メーカーであり、企業理念に「人を大切に、技を大切に」とある通り、人材と技術力を両輪に成長してきた会社です。「人」と「技術」が生み出す「化学の力」を使って社会課題の解決に役立つ製品やソリューションを提供していく、それが当社の存在意義にほかなりません。そして独自の技術で、他社であれば尻込みしそうな難易度の高いものづくりにチャレンジし、それを安定的に生産して、品質と納期を違えることなくお客さまにお届けできることが当社の一番の強みです。
こうして当社のビジネスの全体像を振り返ってみると、お客さまに対してもサプライヤー様に対しても、しっかりした信頼関係を築いてきたことが、当社が長きにわたり事業を継続できた理由であると気づきます。その時代ごとにお客さまが必要とする化学品について、研究開発、サプライチェーン、製造技術、知財管理に至るまで、一連のプロセスをしっかり整備し、地道に繰り返してきたことが今日の信頼につながっているのだと考えています。信頼は実績があるからこそ築かれるものであり、実績なしに信頼を得ることはできません。この信頼関係を今後も大切にし、さらなる成長を目指していきます。
一方、視点を過去から未来に転じてみると、今後も当社が持続的な成長を遂げるには、さらなるビジネスフィールドの拡大が必要となります。国内市場は人口減などで大きな需要増が期待できないことから積極的な海外進出を図っていく計画で、2024年度からは台湾に現地法人を設立し台湾での新たな市場開拓に力を注いでいます。こうしたグローバルビジネス拡大の足掛かりとして期待しているのが、環境貢献製品など社会課題の解決に役立つ製品やソリューションです。これらは当社のビジネスモデルの進化に欠かすことのできないもので、社会に貢献する新たな価値を創造し、それが当社の収益にも貢献するという好循環を生み出していかなければならないと強く感じています。しかし、化学品のイノベーションには、どうしても相応の時間が必要で、いざ開発できた際にタイミングよく大きな需要があるか、その見極めは難しいものがあります。潜在需要の掘り起こし、事業化のタイミング、採算性の見極め、こうした目利きの能力を伸ばしていくことがとても重要であると考えています。また、今後海外へ事業を拡大させていくうえで、グローバルビジネスの視点で活躍できる人材をいかに確保するかも大きな課題です。
日本化学工業らしいサステナビリティ経営の模索は続く
私は2年前の「サステナビリティレポート2023」において「従業員一人ひとりがサステナビリティを自分ごととして考えることのできる、日本化学工業らしいサステナビリティ経営」を目指すことを皆さまにお伝えしました。もちろん、これは口で言うほど簡単なことではなく、今も模索を続けている状態ですが、一歩一歩着実に進化していると思います。
環境への取り組みでは、脱炭素社会の実現に貢献するためCO₂フリー電気への転換を進めています。特に東北地方の2拠点において使用電力の半分をCO₂フリー電気に切り替えたことで、2024年度の全社のCO₂排出量を2020年度比で20%ほど削減しました。2025年度からは、本社を皮切りとして全拠点で太陽光発電の導入を計画しており、創エネへの取り組みを促進していく計画です。さらに2024年度の設備投資案件からICPを導入し、省エネ型設備採用の判断指標とすることでScope1の排出量の削減も促進します。こうした当社の取り組みに対する社外からの評価は高まっており、2024年度のCDPでは「気候変動」と「水セキュリティ」でBスコアを獲得しました。
社会側面の取り組みでは、新たに「サステナブル調達方針」を定め、主要サプライヤーに対しては人権尊重や労働安全を含めたCSRアンケートを実施しています。今後は、当社のサステナビリティ経営に対する考え方をサプライチェーン全体に広めていく考えです。また各拠点では、地域社会との結びつきを深める取り組みを展開しています。2024年度に初めて「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」を活用し、当社の事業所がある自治体に寄付を行ったほか、愛知工場では、地元の小学生を対象にサイエンストークを開催して化学のおもしろさに触れる機会を提供するなど、次世代育成支援にも力を入れています。
ガバナンスとリスクマネジメントでは、特に昨今、ハラスメント問題が企業の存続にもかかわる重大なリスクとなっていることから、2025年1月に「ハラスメント撲滅宣言」を発表し、いかなるハラスメントも許容しないという企業姿勢を明確にしました。併せて、社外取締役には取締役会だけではなく経営会議にもご出席いただくなど活躍の場を広げ、出席できない場合にも迅速な情報共有を行い、常に第三者の視点を入れることで経営の透明性を高める改革を継続しています。
株主・投資家の皆さまへ
幸いにして2024年度の決算は好調と言える結果でした。2025年度は外部環境が極めて読みづらい状況となっていますが、いかなる状況においても業績向上の余地を探り、当社が持続的に成長する道を探り続けてまいります。
当社は、これまでも外部環境にかかわらず、業務の効率化、経費の削減など、不断の経営努力を続けてまいりました。今後は、当社ならではの人的資本経営の一層の充実を図るとともに、AIを含むDXなども活用し、さらなる業務の効率化や職場環境の改善を進めてまいります。
価値観が多様化し、企業に求められる責任も年々増加する中、これからも株主・投資家の皆さまをはじめとするすべてのステークホルダーから「日本化学工業は、社会にあり続けてほしい会社」と思っていただける存在でありたいと願っています。「2030年ありたい姿」の実現に向け邁進する当社のこれからの歩みに、ぜひご期待ください。
サステナビリティについてのお問い合わせはこちらから